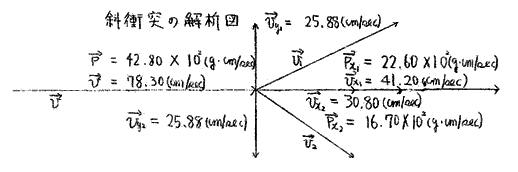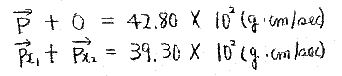静岡県高等学校理科教育研究会 生徒研究発表会 研究発表用冊子
<homepage><history><ronbun><ST1967>(st1967-1.htm) 次ページ(スナップ写真)
日時:1967年昭和42年12月3日 場所:静岡県立三島南高等学校
富士高校物理部・物理班
ストロボによる運動の研究
静岡県立富士高校物理部 声高正紀
【目的】
- 実験装置を自分たちの力で考案、製作すること
- これによって
(1)運動の独立性の存在を確認 (2)斜衝突による運動量保存則を確認 (3)円運動の向心力について (4)分子の熱運動の実態を調べること
【方法】
- 実験装置の作成
光源−乾電池炭素棒を用いてアーク光の製作。
円板ストロボ−ベニヤ板にスリットを切り抜き手回しで回転させた。
グラフ−エナメルで黒く塗装した角材で縦150cm横100cmの枠を作り縦横10cmおきに絹糸をはりわたした。
反射板−ベニヤ板にアルミはくをはった。
【内容】
- 運動の独立の原理の研究
- 自由落下と放物運動の同時撮影
解析の結果鉛直方向は重力による等加速度運動、水平方向は慣性による等速度運動が独立に存在している。
- 斜衝突による運動量保存則の確認
- 2個の白い球体を用意し、1球をガラスの上に静止させておき、他の1球を玉つきの原理を応用して、これに弾性衝突させる。そしてこの衝突の前後の速度を求め運動量の変化を調べる。
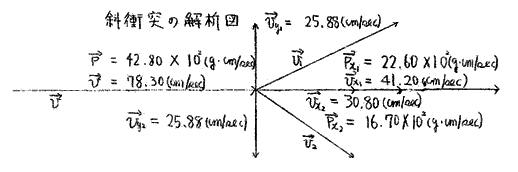
結果
-
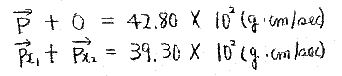
- となりました。
- 約8.5%の誤差範囲内で運動量は保存されました。
- 円運動の向心力について
- 円すい振り子を上から撮影しました。
円運動を起こす原因である向心力はこの場合、糸の張力の水平分力mgtanθである。これはmv2/r に等しくなくてはならない。
ストロボ写真より速度を求めて
mgtanθ=mv2/r
の成立することを認めることができました。
- 分子の熱運動量について
- 分子の熱運動によるブラウン運動の顕微鏡写真をストロボ撮影してみました。
【備考】
- スリットの幅はせまい方がむらがでにくくなる。
- カメラの位置は物体の運動範囲の中心に設置する。
- グラフ−スケールを使用して被写体の位置関係の目安にしようと用いましたけれど、同じフィルムのこまに同時に撮ることは光量の加減によって、わかりにくくなりましたので、別々に撮り(同じ場所にて)印画紙に焼きつける時に二つに重ねました。
- 絞りは1.8〜2.0が最もよかった。
- 回転盤の回転数はストップウオッチによって決定しました。
【方針】
- 今まで行って来ました研究をさらに発展させるためにひきつづいて運動の研究をしていきたいと思います。特にまだ研究の余地のある分子の熱運動をこれからの課題にしたいと思います。
<homepage><history><ronbun><ST1967>(st1967-1.htm) 次ページ(スナップ写真)