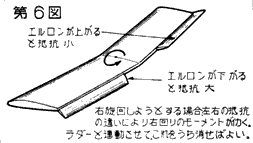
<homepage><history><ronbun><RC1968>(rc1968-4.htm)
| ラジコン技術1968年2月号−4 前ページ 次ページ |
安定牲について
上反角は大きめに4°とりましたし、重心位置もだいぶ下のため考えていたよりずっと復元性が強く、舵のききが悪かったのもこの点に影響があったのではないかと思われます。上反角は2°くらいでもよかったようです。縦の安定は普通の飛行にはじゅうぶんあり、操縦しやすい機体でしたが、宙返りをかるくやったのは意外でした。
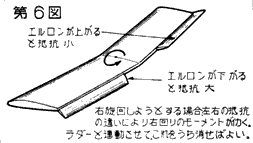 |
| ヨーイングの原因は・・・ |
ヨーイングについて
いままで中・低翼エルロン機は私たちもこなしてきましたが、偏揺れ現象をあまり感じたことはなく、これを感じたのは初めてで驚きました。重心位置が低いからか?上反角が多いのか、縦横比8が影響しているのか、フル・エルロンが悪いのか?私たちにはよくわかりませんが、たぷん上記のものが組み合わさって、この現象を起こしているではないかと思います。もっともライト兄弟もこれにだいぶ悩まされたそうですが…(第6図参照)。
撮影について
真上から撮った写真はブレがほとんど認められませんが、斜めから撮った写真にはブレが出ました。斜めに撮影するときは機体を右肩に倒してとるのですが、機体が復元するときシャッターがきれるので、復元の速度が速いため流れてしまうのではないかと思われます。このことは初めから予想はしてエルロンにしたわけですが、まだ上反角を減らさなければなりませんし、ねじまき(フイルム巻きとり)のときのカメラの積みかえをもっと容易にできる方法を考えなければなりませんし、カメラを斜めに向けてとるようにするのもブレを少なくするよい方法でしょう。
高原に消えたフェニックス
私達班員は親睦をはかり、RC技術の向上を計ろうと富士宮市朝霧高原で高原飛行会を開きました。保科模型店の保科さんも加わり、だいぶ助けてもらい、マルチ3機、シングル数機、それにUコン機も加わり楽しく過ごしたわけですが、メインエベントに飛ばしたフェニックス号、快調にゆったり旋回を続けていましたが、急にノーコン(不幸中の幸いカメラは乗っていませんでしたが)状態になり、まるで大きな鳥が自分の巣に帰るような格好でまっすぐにゆったりと丘の向こうに消えてしまいました。
なかばあきらめかけていましたが、数週間後、「飛行機をみつけたからとりに来てほしい」との手紙が来て無事もどりました。
|
富士高校物理部流体班の略歴 私たちの学校はクラブ活動も盛んで運動部は峡いグランドながらなかなかの成績で、文化部も校舎改築で部室がだいぶ狭くなってしまいましたが、熱心に活動しているようです。特に物理部はアマチュア無線、オーディオ、RC流体、ストロボ、天文、水波の各班から成り立ち各班とのつながりも非常に親密で、互いに刺激しあい活発に活動しています。 |