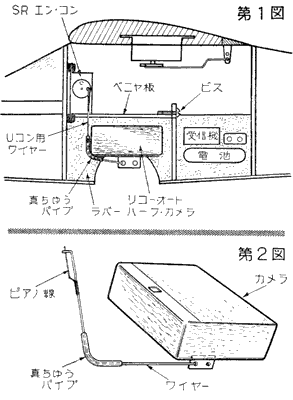
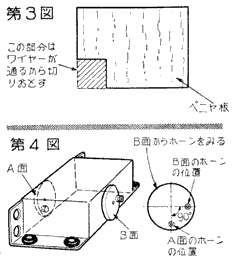
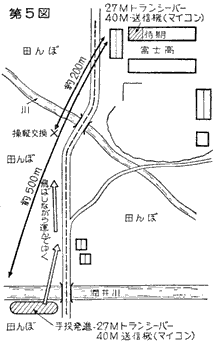
<homepage><history><ronbun><RC1968>(rc1968-3.htm)
| ラジコン技術1968年2月号−3 前ページ 次ページ |
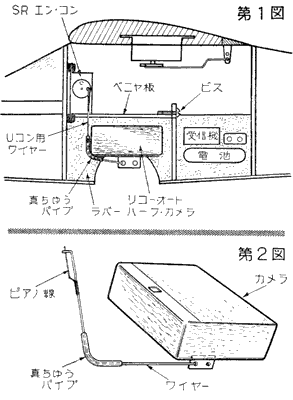 |
| メカ配置とカメラのシャッター連結方法 |
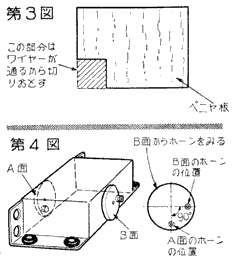 |
| ラバーをおさえるベニヤ板とホーン位置 |
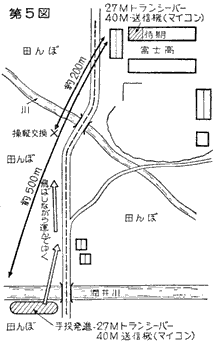 |
| 本機の運行方法をみる |
【メ力配置】 第1図に示すようにいちばん重量の多いカメラを重心位置におきます。SR(三共)のエンコンのホーンの大きさではシャッターを確実にきるには少し足りないようでしたので、少し大きめのヒノデのMS50のホーンと付け替えました。
電池は1本でも回りましたが、ちょっと頼りなく感じたので3Vにしました。サーボとシャッターとの連結は、Uコン用のワイヤーをL字型に曲げた真ちゅうパイプに通して連絡しました(第2図参照)。
底には20mmのホーム・ラバーを接着(接着しないとズレてレンズや露出計をおおってしまうことがあり,われわれも失敗した)、カメラの上部にも10mmのホーム・ラバーをあてがい(第3図)ベニヤ板でおさえます。
エンコン・サーボを動かしてみてパシン!!ジャアーという音が聞こえたらOK、少々のズレでしたらサーボとおさえ板の間にかいものをしてなおせます。なお当然のことですが、エンコン用のホーンとシャッター用のホーンとは90°の位置にセットしておきます(第4図参照)。エンジンがスローからハイになるときシャッターがきれるようにセットしました。
受信機、電池類は後部にゆったりおさまります。フィルムは初めネオパンSS(ASA100)で行ないましたが、大きく拡大しますとハーフ判でもあるし粒子があれますので,ネオパンF(ASA32)に替えてみました。
ブレが少々出たものもありましたが,かえって美しい写真ができました。この場合ASA32となっていますが,カメラが胴体の中におさまっているので露出計のまわりが少々暗く、絞りが開きぎみなようなので,前述のようにカメラのASA32目盛りを50にして写しました。
飛行撮影
製作は月並みになりますので省略します。左・右の翼を作ったり、削りすぎたりしながらも絹を張り、塗装も終って初飛行を試みました。グランドでグライド・テストを行なってみましたが、不安があるのでカメラの替わりにハンダ(約300g)をのせました。
風が相当強く吹いていたこともあったでしょうが、思っていたよりずっとフンワリで「これならいける」ということで、ダウン・スラストを少し増し、その日の夕方に潤井川へ初飛行に向かいました。
風もだいぷおさまりコンディションは上々、手投げ発進でグングン上昇しドッシリした感じで安定もよく、みんな泣いて喜びました。しかし癖が強く、エルロンで修正しましたが、うまくなおらず、舵のききめも悪かったのでエルロンを交換し、ラダーも調整のため可動としました。 処女飛行も無事終り,学校に引きあげて心細かった車輪を強化し、カメラを積み明日の撮影に備えました。学校のグランドから飛行できるとよいのですが、狭くて回りには校舎をはじめ体育館、バックネット、寮、高圧線などが取り巻いているので、潤井川の土手で離陸して学校に運ぷ方法をとりました。初め潤井川上空で旋回をしてから学校上空へ運ぼうとしましたが途中でエンスト、潤井川周辺を十数枚撮影、2回めは苦労して学校上空まで運びましたが、先に話したように、ホーム・ラバーがレンズをおおっていたためかフィルムは透明、しかし潤井川上空の写真はなかなかよく撮れていました。
それから約20日後に27Mcトランシーバ、40Mc送信機2台を用意して風も少なく交通量の少ない朝6時に集合直ちに潤井川に向かいました。潤井川の上空でじゅうぶん高度をとり、エンジン・スローにして第5図のような方法で旋回させながら運びました。
トランシーバで常に「癖」、「エンジンの調子」、「舵のききぐあい」、などの連絡をとっていきます。また操縦者交代の合図もこれで行ないます。この日は今までにない長時間飛行のためかエンジンを止めるビスがゆるみ、付近の田んぼに不事着陸しました。
ついに新校舎撮影に成功しました。おしくも全面撮影されているものはあまりありませんでしたが……
初めての試みであり、シングルで30クラスを使うことなど経験もなく、わからないことだらけでやってみなければわからないという状態でした。