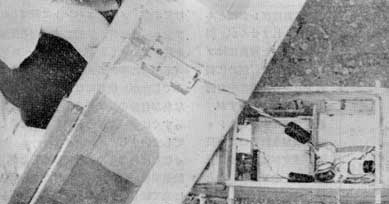
<homepage><history><ronbun><RC1968>(rc1968-2.htm)
| ラジコン技術1968年2月号−2 前ページ 次ページ |
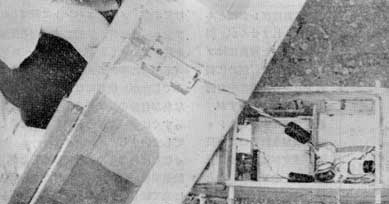 |
| 本機のメカ搭載をみる(SRサーボ、SRエンコン・サーボ) |
【胴体】 縦の安定もじゅうぶんにとらなくてはなりません。胴体の場合は翼と違って復元性を大きくして操縦を容易にするため、テール・モーメントを大にとりました。
翼幅が1600mmあるのに全長が954mmしかなく見たところテールが短いように感ずるかもしれませんが、主翼の縦横比が1:8と大きくとってあるので翼弦が短くなり、テール・モーメントが大でも後部が短かくなります。
ノーズ・モーメントについては、ゼロ戦やトーラスのようなノーズの小さいものを作ってみたいと思いましたがテールを比較的長くとってあります。メカが重心より後部にすべてのせることになり、後が重くなることが考えられますので、長めにとって1.25にしました。胴体の太さはメカニズムがらくに入り、サーボなどのひっかかりのないように太くしました。
【尾翼】 垂直尾翼は軽量化のため5mmバルサを組み、ラダーは当初は特別に設けませんでした。しかし3〜4回飛行しているうち、癖の修正がうまくいかず,めんどうであったため、ラダーを尾翼から切り離し、可動式にしました。
実は設計が終って製作をはじめたころに部員の友人がこの計画を聞き、30と19を交換してあげましょうということで交換してくれましたので、OSMAX30RCを使うことになりました。
そこで縦の安定をより増すため水平尾翼の面積は17%増し、主翼面積の26%としました。また運搬に便利なように取りはずし可能にしました。
【補強】 エンジンが30になったので19のときの設計より補強を強化しました。シャッターを押すときエンコン・シャッター連動なので、回転がスローになったりハイになったりするわけで、特にスローのときの振動は大きなものです。
19エンジンとしての設計は、ヤングサンダーと同じような軽量化を重視したような補強でしたが「多少重量が増しても30エンジンなら」ということで補強を変更しました。しかし軽く仕上げるということはいつも頭におかなければなりません。
【その他】 底の撮影用窓はリコー・オート・ハーフのレンズ・ファインダー・露出計のある長方形の大きさよりやや大きめにあけましたが、普通に外に出して写すときより絞りが開きぎみであるようで、ネオパンF(ASA32)をカメラのASA目盛りの50でセットするとちょうどよく写りました。
車輪は滑走離陸させるわけでありませんから簡単な2車輪式にしました。
 |
| 本機から潤井川付近を撮影、写真右下の所に私達(班員)がいます。 |