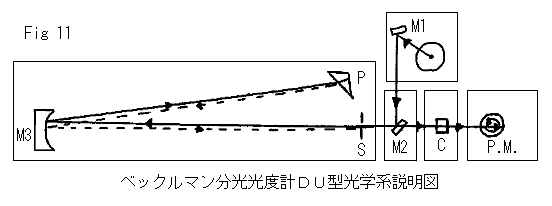
不可能であることを示している。
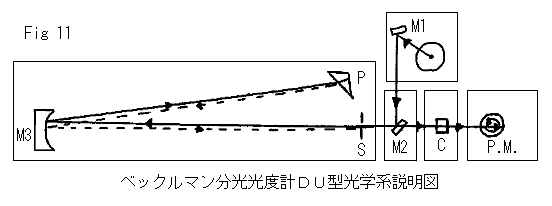
Fig11は分光光度計の初期のもので、ドイツのBeckmanによって作られた。東京工業大学の研究室の先生の説明によると、大正時代日本に3台輸入されたそうである。また、この機械は高分解、高分散度が得られやすいため広く用いられたそうである。著者も、東工大で見たが、大正時代に他国でこのような精密な機械が作られていたかと思うと、おどろくばかりであった。大きさは、持ち運びが可能なくらい小型であった。ガンコで、いかにもドイツ製らしかった。
| Fig11において、 | M1,M2 | ……平面鏡 |
| M3 | ……凹面鏡 | |
| P | ……プリズム(PRISM) | |
| S | ……スリット(SLIT) | |
| C | ……資料 | |
| P.M. | ……光電子増倍管(フォトマルチプライヤー) |
この分光器において注目すべき点は、資料がP.M.の前にあり、分光された光を資料にあてている所である。また、同一光路を2度使っているところに、魅力を感じる。