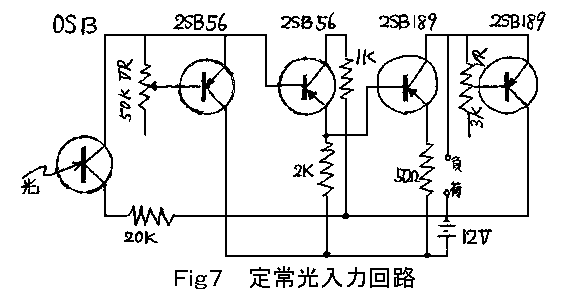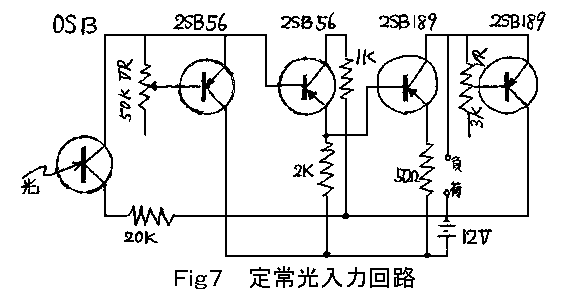
CDSは立ち上がりが遅く、光を感じてすぐ電流になおすには手間がかかる。)以上3つの点で、他をぬいて良い特性を有していたからです。
また、本体に組み込んだ増幅回路はありふれた回路で、資料はころがっています。そして本体に増幅器を組み込んだ理由があります。それは、もし組み込まなかったら、受光機と負荷の距離が2〜3mもあるから、ノイズを拾いやすいではないかと思ったからです。だから本体で1段増幅させて、負荷までシールド線でひっぱり、負荷の前段でもう一度増幅を2〜3段かけているのです。[回路図はFig7に示す]
測定時においてPTrの前にスリットをおくということを説明すると、まず、1000Åの帯スペクトルが10cmに広がったとします。すると、100Åが1cm、10Åが1mmに広がっていることになります。さてもし仮に分解能10Åを要求した場合受光機の受光面は1mmの幅が必要になります。どうしたらPTrの受光面ができるでしょう。それはPTrの受光面積を狭くすればよいのです。それにはスリットを使えばよいのです。このような理由でPTrの前にスリットをつけたのです。
現在使用している回路はFig7に示す。しかし、PTrの受光面積がせまいために、OS13を多くするため、OS13を直列につなげる回路に替えつつある。結果はまだ出していない。