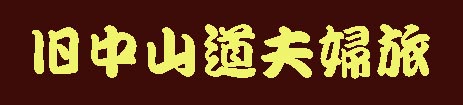
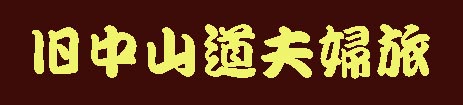

“「垂井の泉」と大ケヤキ 垂井宿” |


 やがて街道は三たび国道21号線に出て、そのあとしばらくは国道を進む。午後1時19分、300mほど歩いた左側に「西首塚」の史跡があった。(右写真)石柱に「史蹟 関ヶ原古戦場 西首塚」とあり、国の史跡になっている。
やがて街道は三たび国道21号線に出て、そのあとしばらくは国道を進む。午後1時19分、300mほど歩いた左側に「西首塚」の史跡があった。(右写真)石柱に「史蹟 関ヶ原古戦場 西首塚」とあり、国の史跡になっている。 200mほど進んだ国道の右側に常夜燈があった。(左写真)竿部に両皇大神宮と刻まれている。珍しいのは脇に大きな御幣が立てられていることである。和紙の部分がかなり萎れているから立てたままにしてあるようだ。
200mほど進んだ国道の右側に常夜燈があった。(左写真)竿部に両皇大神宮と刻まれている。珍しいのは脇に大きな御幣が立てられていることである。和紙の部分がかなり萎れているから立てたままにしてあるようだ。 午後2時20分、西町交差点から東へ150mほど進み、東首塚の標識に従って左折すると、突き当たりが八幡神社である。入口右手にスダジイの巨木があった。(右写真)「日本の巨樹・巨木林」によると、幹周囲7.8m、主幹3m、樹高10mとなっている。主幹が大きく裂けてはらわたをさらしているが、若々しい支幹が周りを囲み威厳を保っている。案内書には本陣から移したと書かれているものがあるが、これだけの巨木を移設することはほとんど不可能だと思われるので、元本陣庭の隅にあったものが庭ごと八幡神社の境内に取り込まれたのが真実であろう。案内板では表現がぼかされている。本陣のスダジイとくれば、「関ヶ原宿の巨木」(二本目)に指定しなければなるまい。ところで案内板の「スタジイ」は「スダジイ」が正しい。時々同じ間違いをみることがある。
午後2時20分、西町交差点から東へ150mほど進み、東首塚の標識に従って左折すると、突き当たりが八幡神社である。入口右手にスダジイの巨木があった。(右写真)「日本の巨樹・巨木林」によると、幹周囲7.8m、主幹3m、樹高10mとなっている。主幹が大きく裂けてはらわたをさらしているが、若々しい支幹が周りを囲み威厳を保っている。案内書には本陣から移したと書かれているものがあるが、これだけの巨木を移設することはほとんど不可能だと思われるので、元本陣庭の隅にあったものが庭ごと八幡神社の境内に取り込まれたのが真実であろう。案内板では表現がぼかされている。本陣のスダジイとくれば、「関ヶ原宿の巨木」(二本目)に指定しなければなるまい。ところで案内板の「スタジイ」は「スダジイ」が正しい。時々同じ間違いをみることがある。 神社の左脇を通って北へ行く道はかっての北国脇往還だという。その道をJR東海道を陸橋で越えた向こう側の右手に朱塗りの建物が見えてきた。これは徳風会名古屋支部によって昭和15年に建てられた東首塚の供養堂である。(左写真)東首塚は供養堂の北隣りにあった。
神社の左脇を通って北へ行く道はかっての北国脇往還だという。その道をJR東海道を陸橋で越えた向こう側の右手に朱塗りの建物が見えてきた。これは徳風会名古屋支部によって昭和15年に建てられた東首塚の供養堂である。(左写真)東首塚は供養堂の北隣りにあった。 東首塚には目印に椎の木が植えられ、根上がりした根っ子が玉垣で囲われた塚を包んでいるように見える。(右写真)
東首塚には目印に椎の木が植えられ、根上がりした根っ子が玉垣で囲われた塚を包んでいるように見える。(右写真) 東首塚に左側には「首洗いの古井戸」があった。(左写真)石枠で固め竹で編んだ蓋がされていた。戦いの後、西軍の主な武将の首実検が行われた。それに先立ちこの井戸水で首を洗って実検をやり易くしたのである。(なお案内板の「首実験」はもちろん「首実検」が正しい。ワープロで打つと間違えそう。)
東首塚に左側には「首洗いの古井戸」があった。(左写真)石枠で固め竹で編んだ蓋がされていた。戦いの後、西軍の主な武将の首実検が行われた。それに先立ちこの井戸水で首を洗って実検をやり易くしたのである。(なお案内板の「首実験」はもちろん「首実検」が正しい。ワープロで打つと間違えそう。) 街道筋に戻るとすぐ左側にそれらしい門に「脇本陣 関ヶ原宿」との木看板の掛かった家があった。(右写真)脇本陣跡で門の右側に至道無難禅師誕生地の石碑が建っていた。
街道筋に戻るとすぐ左側にそれらしい門に「脇本陣 関ヶ原宿」との木看板の掛かった家があった。(右写真)脇本陣跡で門の右側に至道無難禅師誕生地の石碑が建っていた。
 また次の左角には二階建ての大きな町屋とうしろに工場らしき建物や煙突まで見えた。(右写真)側壁の前面に大きく看板が書かれていたが、剥げて錆びてほとんど見えなくなっていた。写真を拡大してみると、「関ヶ原たまり」と何とか読めた。「たまり」は広辞苑によると、
また次の左角には二階建ての大きな町屋とうしろに工場らしき建物や煙突まで見えた。(右写真)側壁の前面に大きく看板が書かれていたが、剥げて錆びてほとんど見えなくなっていた。写真を拡大してみると、「関ヶ原たまり」と何とか読めた。「たまり」は広辞苑によると、 さらに300mほど進んだ所から、街道は400mほど国道21号線からすぐ北側に並行する道を行く。途中、一部遊歩道のように整備され、松の幼木が植えられ松並木が復元されていた。
さらに300mほど進んだ所から、街道は400mほど国道21号線からすぐ北側に並行する道を行く。途中、一部遊歩道のように整備され、松の幼木が植えられ松並木が復元されていた。 この桃配山で900年を隔てた共に東軍の大海人皇子と家康が出会う。そして共に勝者となり、天下に号令する立場となった。
この桃配山で900年を隔てた共に東軍の大海人皇子と家康が出会う。そして共に勝者となり、天下に号令する立場となった。 元に戻って、再び国道21号線のすぐ北側に並行する中山道に入る。すぐに松林の残る街道筋となる。(左写真)
元に戻って、再び国道21号線のすぐ北側に並行する中山道に入る。すぐに松林の残る街道筋となる。(左写真) その松林の途中のポケットパークに「六部地蔵」を祀った祠があった。(右写真)
その松林の途中のポケットパークに「六部地蔵」を祀った祠があった。(右写真) 「六部地蔵」から関ヶ原町野上の集落を15分ほど東進した左に、注連縄と榊で飾られた鳥居があった。(左写真)その脇に、「式内 縣社 伊富岐神社」と刻まれた石柱が立っていた。
「六部地蔵」から関ヶ原町野上の集落を15分ほど東進した左に、注連縄と榊で飾られた鳥居があった。(左写真)その脇に、「式内 縣社 伊富岐神社」と刻まれた石柱が立っていた。 さらに800mほど進むと、新道が交錯してややこしくはなっているが、国道21号線を渡って国道の南側の垂井町日守の集落に入る。
さらに800mほど進むと、新道が交錯してややこしくはなっているが、国道21号線を渡って国道の南側の垂井町日守の集落に入る。 「垂井一里塚」の東隣には入母屋造り平家の「日守の茶所」があった。(左写真)建物はよく整備されてそれほど古いものとは見えなかった。
「垂井一里塚」の東隣には入母屋造り平家の「日守の茶所」があった。(左写真)建物はよく整備されてそれほど古いものとは見えなかった。
 街道はもう一度国道を渡り、JR東海道本線の踏切を越えて垂井宿へ入っていく。途中斜めに右折、小川を渡った右側に、「垂井宿西の見付」の案内板があった。
街道はもう一度国道を渡り、JR東海道本線の踏切を越えて垂井宿へ入っていく。途中斜めに右折、小川を渡った右側に、「垂井宿西の見付」の案内板があった。 垂井宿を3分ほど歩くと、左側に本龍寺がある。(左写真)山門右側の高い建物は鐘楼かと思ったが、鐘楼は左側にある。後日ネットで調べた所、太鼓楼であった。鐘と太鼓をどのように打ち分けたのであろうか。左側には山門右前に「明治天皇垂井御小休所」の石碑が立っていた。明治11年10月22日、北陸、東海の御巡幸の際、本龍寺で休憩をとられたという。
垂井宿を3分ほど歩くと、左側に本龍寺がある。(左写真)山門右側の高い建物は鐘楼かと思ったが、鐘楼は左側にある。後日ネットで調べた所、太鼓楼であった。鐘と太鼓をどのように打ち分けたのであろうか。左側には山門右前に「明治天皇垂井御小休所」の石碑が立っていた。明治11年10月22日、北陸、東海の御巡幸の際、本龍寺で休憩をとられたという。 明治になって脇本陣から移築したといわれる門と玄関は右写真の山門とその奥に見える玄関である。(右写真)
明治になって脇本陣から移築したといわれる門と玄関は右写真の山門とその奥に見える玄関である。(右写真) 本龍寺境内の左手奥に「時雨庵」がある。(左写真)この建物は先ほどの「日守の茶所」の秋風庵を建てた化月坊がこの時雨庵も建てたという。そういえば入母屋の造りもどこか似ている。しかし秋風庵と違って、時雨庵はかなり痛みが激しいようだ。由緒ある建物であるならば修復する必要があると思った。
本龍寺境内の左手奥に「時雨庵」がある。(左写真)この建物は先ほどの「日守の茶所」の秋風庵を建てた化月坊がこの時雨庵も建てたという。そういえば入母屋の造りもどこか似ている。しかし秋風庵と違って、時雨庵はかなり痛みが激しいようだ。由緒ある建物であるならば修復する必要があると思った。 時雨庵脇の庭には、幾面もの句碑が立つ中に「作り木塚」があった。(右写真)
時雨庵脇の庭には、幾面もの句碑が立つ中に「作り木塚」があった。(右写真) 本龍寺を出てすぐ街道右側に江戸後期の商家が残されていた。(左写真)2階は黒壁、虫籠窓で軒下にはぬれ蓆を掛ける釘がついている。(左写真の円内)その釘も鍛冶屋が打って造ったものであろう。
本龍寺を出てすぐ街道右側に江戸後期の商家が残されていた。(左写真)2階は黒壁、虫籠窓で軒下にはぬれ蓆を掛ける釘がついている。(左写真の円内)その釘も鍛冶屋が打って造ったものであろう。 続いて交差点右に道路を跨いで南宮大社大鳥居が立っていた。(右写真)両脇に常夜燈も立っている。「南宮大社」は美濃国一の宮でこれより南に1.5km行った南宮山の麓にある。金山彦命を祀る鉱山、金属業の神様である。
続いて交差点右に道路を跨いで南宮大社大鳥居が立っていた。(右写真)両脇に常夜燈も立っている。「南宮大社」は美濃国一の宮でこれより南に1.5km行った南宮山の麓にある。金山彦命を祀る鉱山、金属業の神様である。 午後4時36分、この鳥居の角を右折して200mほど行った右側に「垂井の泉」がある。(左写真)ケヤキの根元から今も湧き出している泉は「垂井」の地名の由来ともなっている。芭蕉は本龍寺で冬ごもりをしたとき、この泉を訪れ、
午後4時36分、この鳥居の角を右折して200mほど行った右側に「垂井の泉」がある。(左写真)ケヤキの根元から今も湧き出している泉は「垂井」の地名の由来ともなっている。芭蕉は本龍寺で冬ごもりをしたとき、この泉を訪れ、  泉のそばの大ケヤキはなるほど太い。しかし傷みも大きくて正面にかなり目立つ補修がされていた。(右写真)しかし、これを置いて「垂井宿の巨木」とすべき木はあるはずはないので問題なく指定である。
泉のそばの大ケヤキはなるほど太い。しかし傷みも大きくて正面にかなり目立つ補修がされていた。(右写真)しかし、これを置いて「垂井宿の巨木」とすべき木はあるはずはないので問題なく指定である。 「垂井の泉」の上に専精寺というお寺がある。専精寺のあたりには関ヶ原の前には垂井城があった。「垂井の泉」の南側に登った所に「垂井城跡」の石碑があった。(左写真)石碑の周りには椿の花びらが散り敷いて見ものであった。
「垂井の泉」の上に専精寺というお寺がある。専精寺のあたりには関ヶ原の前には垂井城があった。「垂井の泉」の南側に登った所に「垂井城跡」の石碑があった。(左写真)石碑の周りには椿の花びらが散り敷いて見ものであった。 南宮大社の大鳥居まで戻って、垂井宿を行く。すぐに右側にかって垂井宿の問屋であった金岩家の建物があった。(右写真)
南宮大社の大鳥居まで戻って、垂井宿を行く。すぐに右側にかって垂井宿の問屋であった金岩家の建物があった。(右写真) その先で宿は道が北へずれて明らかに桝形も形状を示していた。(左写真)ここが宿の東の入口にあたるのであろう。
その先で宿は道が北へずれて明らかに桝形も形状を示していた。(左写真)ここが宿の東の入口にあたるのであろう。 桝形の角に現在もなお営業している旅籠亀丸屋があった。(右写真)
桝形の角に現在もなお営業している旅籠亀丸屋があった。(右写真)



  |
 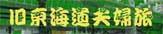 |

 |
このページに関するご意見・ご感想は: |