図 1 - 3 ライン分岐例
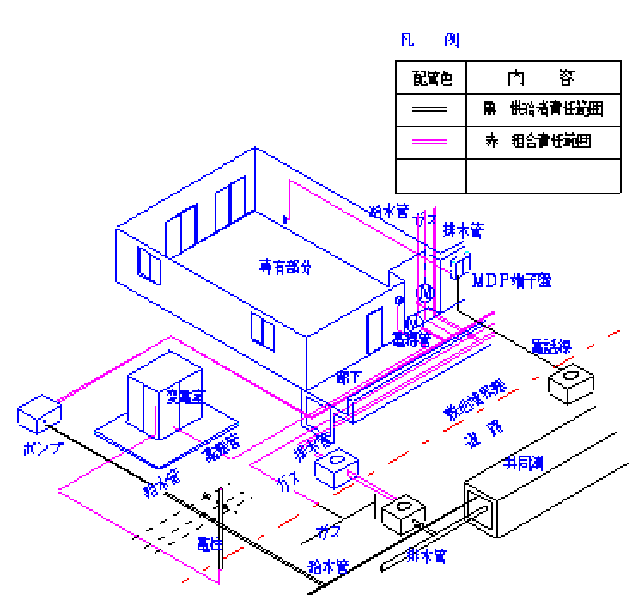
|
第 一 章 マンションとは |
|
3. 専有部分と共用部分
区分所有法第2条3・4では用語の定義として「専有部分」「共用部分」 を定め、第4条では共用部分の目的等を規定している。第2節(11〜21条) では、共用部分の役割について専有と共有の違いを記述してある。共用部分には階段、外廊下等区分所有者が誰でも使用できる部分と、バルコニー等限られた人だけが使用できる部分(これを専用使用権部分と云う)とに分けられる。又、第67条で団地共用部分として団地内で共用部分を定める法律が追加されている。区分所有法等の条文では「専有部分」「専用使用権」「共用部分」「共有」等の表現があるが語意をよく理解して読む必要がある。 ● 建物の「専有部分」と「共用部分」 区分所有法では「専有部分」「共用部分」を大まかに分類しているが、それだけでは不充分であり補足的に「規約」で少し詳しく「専有部分」と「共用部分」とを区分けしている。これが「中高層共同住宅管理規約(以下管理規約という)」である。(付録参照)この規約を雛形にして各管理組合が専有部分、共用部分として規約や使用細則を規定している。そこから先は「常識的判断」に委ねられているが、「常識」が時代と共に変化しているのでもう少し具体的に施設、運営両面から共用部分の範囲を明確にすることが求められている。又、標準管理規約と管理組合の管理規約が必ずしも同じとは限らないので所属する管理規約をよく読み、専有部分と共有部分を確認する必要がある。 例を挙げると法律及び規約のどちらも構造体の個人の専有権を認めていない。かといって空間の中で生活している訳でもない。実際には建物躯体と専有部分とは金属類、接着剤等で接続、接着されている。標準管理規約では躯体を傷つけたり、孔をあけることを原則禁止しているが新築時にのみこうした行為が許可される根拠は何故か?室内改修工事時に古い金属類が再使用できない場合、勝手に工事をするとトラブルになる可能性もある。また、専有部分にある設備配管については、専有部分とすると定めてあるが躯体内の配管等の責任範囲は何処までなのかの基準について記述している例は少ない。専有部分から漏れだした給排水等は、専有者側に過失があれば専有者の責任になる可能性があるので取り扱いに注意を要する。 ● ライフラインの分岐 |
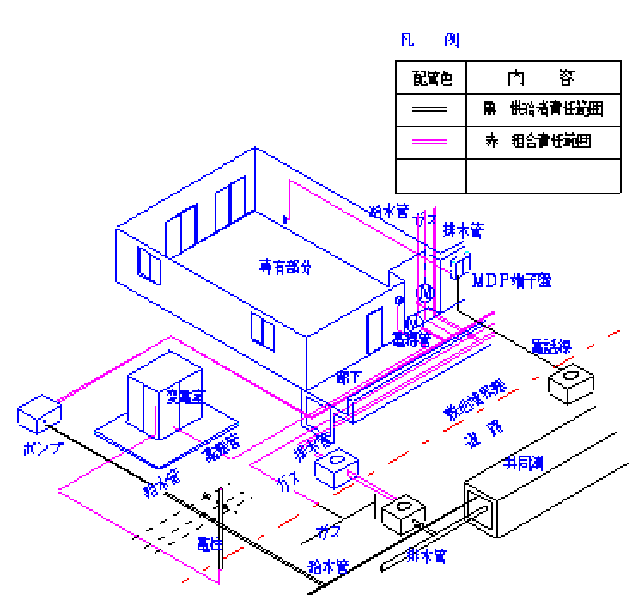
|
|
集合住宅の基本は一棟の建物として取り扱われる事で、ライフラインの接続も当然一棟の建物に対して接続後各戸に分岐される。これが集合住宅の基本であり運命共同体のゆえんでもある。 電気の配線、上下水道等配管の配給会社(役所)との分岐はどうなるか?電気は電力会社の電気室、上水道はメ−タ−、下水道は官民境界排水桝、ガスは敷地境界、電話線は端子盤までが一般的な共用部分の責任範囲となる。専有部分の場合は、パイプスペース、メーターボックスと専有部分との境、或いはメーターから先までが専有部分であり区分所有者の責任範囲になるが、管理規約によって異なる場合があるので確認する必要がある。 |
| 前へ 目次へ | 次へ |