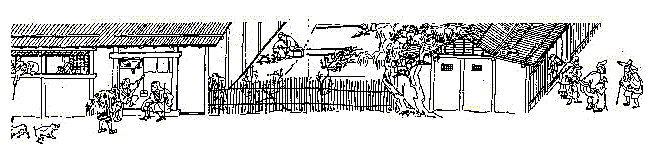● 近代の集合住宅
明治以降になると長屋の建て替え時期に併せてアパート建築物が出現した。当時のアパートは比較的高級所得サラリーマンを対象としていて(財)文化普及会が建築した「御茶ノ水文化アパート」が代表的アパートである。関東大震災後に被災者用住宅建設の目的で財団法人同潤会が「管理者を配置する。賃貸を原則とするが分譲する場合もある。」等を規約として設立された。代表的な建築物である昭和8年竣工の「江戸川アパート」は現在も使用されている。当初の建築は鉄筋コンクリート造地下1階地上6階建て総戸数260戸で、エレベータ設備もあり現代マンションのモデルといわれている。
太平洋戦争後に新形式の集合住宅「公営住宅51C型」が設計され昭和30年台前半に「2DK」タイプの公営住宅が完成した。そこにはダイニングキッチンが「食寝分離」等を目的として図面化されている。それ以降の昭和30年代後半から今日までマンションブ−ムが続いて急速な発展を遂げているが、マンション初期の
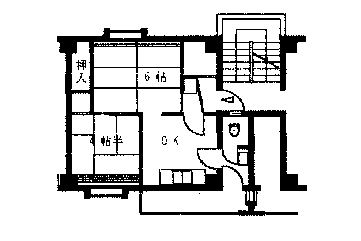
|
● 海外との比較
日本と海外の集合住宅を比較してみると、日本のマンションは「うさぎ小屋」と例えられるように狭いという先入観が強いが、あるデータよれば、東京、パリ、ロンドンの大都市集合住宅の広さにはあまり差がなく一戸当りの平均住戸面積に若干の差がある程度である。しかしアンケートの評価では日本人の狭さに関する不満度が高いとしている。調査からは必ずしも日本のマンション面積の平均値が狭いとは言えず、住民の意識として概念的に狭いと感じているのかもしれない。
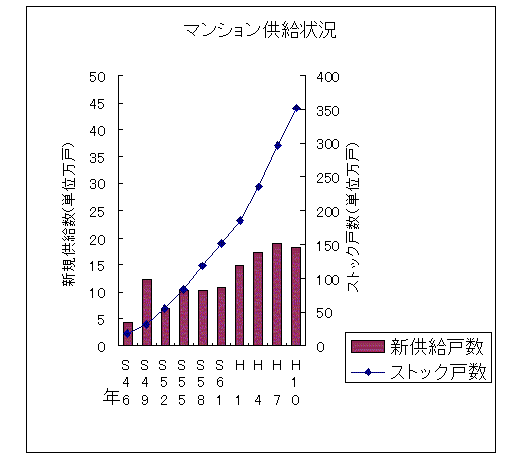
|