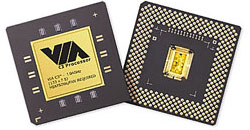cpu > [基本知識]
巷には色んなコンピュータが出回っています。そしてその中には必ず「CPU」が搭載
されています。秒進分歩の分野でもあるので、うっかりしてると、あっというまに浦島太郎に(^^;
用語をクリックすると解説にジャンプします
[CPU(MPU)] CPU(Central Processing Unit)、又はMPU(Micro Processing Unit)、
日本語だと「中央演算処理装置」とか言われたりします。コンピュータの目的でもある"計算"を行って
いる一番メインの装置です。大型コンピュータなどでは複数個のプロセッサで処理させることもありますが、
一般的なパソコンではCPUは1個である場合がほとんどです。
[動作周波数(クロック数)] ICはクロック信号に合わせて動作しています。この信号でタイミングを取ることで、
CPU内部の各部分が論理的に正常に動作できるわけです。動作周波数とは、このクロック信号が1秒間に何回
発生するのかを表しています。同じCPUであれば当然周波数が高ければ、それだけ性能(計算能力)が高い事
になります。
[キャッシュメモリ] パソコンのメモリと言えば、だいたいマザーボード上に載っているメモリカードの事になりますが、
CPUでプログラムや画像、音楽などのデータを処理する為にはそうしたプログラムやデータをCPU内部に持ってこなければ
なりません。しかし、ここで重要な問題が!CPUがあまりにも高速なので、メモリアクセスをしている間、CPUはなにも
する事がなくてとっても暇になってしまったのです。これではせっかくCPUが高速になっても意味がありません。そこで、
頻繁に使われるプログラム中のコードやデータを、一時的にマザーボードのメモリよりも高速(でも高価)なメモリに保存して、
そこにCPUがアクセスする方式が考え出されました。これがキャッシュメモリです。
[FSB(Front Side Bus)] マザーボード上にあるメモリモジュールや拡張スロットとCPUとを接続している経路の事。又はそこから
転じてその経路の動作周波数の事をいい、CPUのスペックでFSBという場合には後者の意味で使われます。
キャッシュメモリの項でも書きましたが、マザーボードに乗っかっているメモリなどへのアクセスはCPUの処理速度に比べると
かなり遅いものです。その遅い部分の速度を底上げすればパソコン全体の処理速度もアップするので、この数値が大きいほうが
システム全体のパフォーマンスは良いと言えます。
[クロック倍率(Bus Ratio)] CPUの動作周波数はFBSの動作周波数をベースに作られています。このFBSを何倍にしてCPUクロックを
生成しているのかを表しているのが、クロック倍率(Bus Ratio)です。
[TDP(Thermal Design Power)] 日本語訳は「熱設計時電力」。CPUは計算をする為に電流を流しています。一般的に高速なCPUほど
多くの電力を必要としていますが、そのエネルギーは全て計算に消費される訳ではなくて大部分は熱として放出されます。特に
近年のCPUは100Wを越えるものも出てきており、適切な放熱を施さないと自分が発生させる熱でCPU自身を破壊してしまうことも
あるのです。
[SIMD(Single Instruction/Multiple Data)] 1つの命令で複数のデータを処理する高速化手法です。IntelからはMMX、それに追随してAMDからは
3DNow ! といった名称で始まりました。現在ではSSE(Streaming SIMD Extensions)という拡張命令が一般的になっています。主に
マルチメディア(音声・画像・動画)などの処理で頻繁に使われるものを高速に処理できるよう、工夫が施されているようです。
[プロセスルール] 現代のCPUは、コアチップ(演算回路や高速キャッシュ)と周辺回路などから構成されるのが一般的ですが、 このコアチップの配線の幅(電流が通る配線ですね)はどんどん微細化しています。2004年では90nm(90ナノメートル)のものが主流に なってきています。リーク電流やCPUで使われるコンデンサの増加などの問題によって、プロセスルールの微細化=省電力とも 言えなくなってきていますが、一般的には同じ規模のCPUにおいてこのプロセスルールの小さいCPUの方が電力消費が少なく、 発熱も少ないと考えられます。 配線が微細になるほど熱には弱くなるので、最近のCPUの廃熱には十分注意が必要になります。
[パイプライン]
[マルチプロセッサ]
[ダイ]
[ダイサイズ]
[開発コード名(内部コード名)]
[ムーアの法則]
[x86アーキテクチャ]
[IA-64]
[x86-64テクノロジ]
...随時追加中(^^)しばらくお待ちくださいね。 |